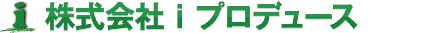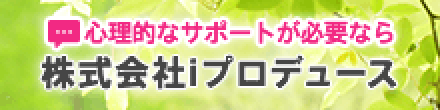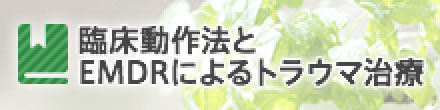ADHDは、概念・診断基準作成段階での製薬会社絡みの利権があったとのではないかという疑念があり、ADHD概念発祥のアメリカでは、10%を超える児童がADHDと診断されています。
発達障害の診断は、医師の主観によるために、アメリカのようにADHDが10%、自閉症スペクトラムが多く見積もって2%となる場合もあれば、仙台市のように
http://blog.canpan.info/haxtutatusien/img/57/2006_soudan.pdf
発達障害として訪れた児童のほとんどを自閉症圏内の問題として診断(652人)して、ADHD診断(8人)をしない場合もあります(これは平成18年のデータ、なおこのデータではDSMのADHDではなく、ICDの「多動性障害」を用いている)。
ちなみに現在、仙台市の児童の約11人に1人が何らかの発達障害等の相談をこちらの医療・相談機関にしています。
ADHDは、確かに気質・性格的な多様性の問題として平均から一定の量的差異をもった場合に診断が可能であると考えられますが、その場合、標準偏差から2SD以上の差を持って生まれる確率(多動である確率)は統計的に、約2%であるはずです。
現場の感触としては、2%以上の児童が、質的に異なる不注意・多動・衝動性のいずれかの問題を抱えていると見ています。つまり、製薬会社の利権によって大目に診断されたり、医師の主観によって診断されなかったりすることがあったとしても、やはり診断されるべき状態の児童が存在することには疑いを持っていません。
しかしながら、不注意・多動・衝動性のいずれかの問題は、遺伝的な要素によってもたらされる(双生児研究では一致率が極めて高い)場合の他、環境要因によっても生じることがあります。震災後に過覚醒のため授業に集中できなくなったり、ストレスのためにイライラして他人に当たったりすることは多くの人に理解されることと思います。
虐待によって、脳の発達が阻害されエピジェネティックな変化が生じ、震災後の時間経過やストレスからの解放によって一時的な行動異常が回復するプロセスとは異なり、環境因子によって「発達障害になる」(ようにみなされる)ことがありえます。
このような機序の他、機能不全家族によって影響を受けるアダルトチルドレン(の児童期)におけるピエロやスケープゴートなどもADHD的な問題行動を呈します。
片親疎外の状態にある子どもの一部も、無意識の葛藤を抱えていて、その問題が意識に上がりそうになると(別居親を蔑んで同居親の安定をもたらしていた戦略が崩れる危機、すなわち面会交流が開始される危険性が生じると)、行動化としての問題行動(観察されるADHD様の症状)が生じることがあります。
ADHD診断の問題となるのは、診断を下す専門家とされる医師は、こういった背景について無知あるいは無視して、報告者(多くは子どもを連れて来た一方の親)の話を根拠にして診断を下すことです。
夫婦仲が良く、環境因子に問題がない場合で乳幼児から一貫してその症状を呈していた場合には診断による本人への心理治療的介入や親教育プログラム、そして必要な場合(自傷他害のリスクが副作用や依存症のリスクを上回る場合)の最小限の薬物療法が有効ですが、医師は、夫婦仲について聴取せず、環境因子の調査を行わずに診断します。
その結果、子どもが呈している症状が、我々大人へのメッセージやサインである場合であっても、一方の親の心理的安定や夫婦間葛藤を有利に進めるための正当化のために利用されることになる場合があります。
これは、ADHDに限らず、自閉症スペクトラム(以下ASD)においても同様ですが、特にASDと診断された場合には、環境変化のストレスを避けるために面会交流を行うべきではないという診断書を利用する監護親(とそれを教唆する弁護士)がいます。
発達障害者支援法では、発達障害者がその障害のために社会参加が妨げられてはならないとされ、家族への支援の必要性が謳われています。つまり、ASDであることを理由に児童の成長に有効である面会交流を妨げることはあってはならず、環境変化を少なくする方策、あるいは面会交流を実現するために必要な家族(監護親・非監護親)への助言・指導こそ診断した医師によってなされなければならないと言えます。
発達障害を診断する医師の方々には、よくよくご留意ただければと存じます。